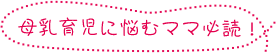

いざ母乳育児を始めると、ときには「これって、ど~したらいいの?」と悩むことも…。
よくある"おっぱいトラブル"の原因&解決策を紹介します。
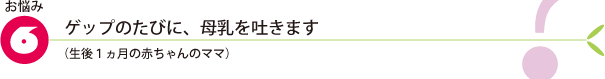
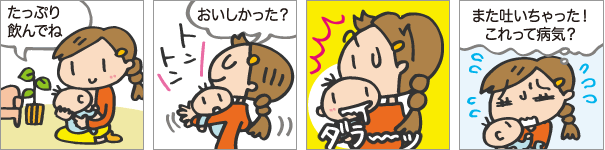
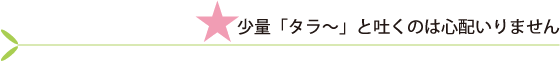
ゲップをしたとき"いつ乳"といって「タラ~」と少量母乳を吐くのは心配いりません。
赤ちゃんの胃は未発達で、大人のように胃の入口が閉まっていません。また形もまっすぐに近いため、背中をトントンするなどちょっとした刺激で、胃の中のものが逆流して吐きやすいのです。
授乳後は、5~10分くらい、しばらく縦だっこをしてあげるとよいでしょう。
また授乳のときは、赤ちゃんが大きく口を開けて乳輪まで深くくわえるのが理想ですが、乳首だけに吸いつく浅飲みだと、空気を飲んでゲップをしたとき吐きやすくなるので注意してください。
ちなみに受診が必要なのは、噴水のように勢いよく吐くときです。"肥厚性幽門狭窄症"(ひこうせいゆうもんきょうさくしょう)といって胃と腸を繋ぐ部分が狭いために吐く病気もあるため、早めに小児科を受診しましょう。
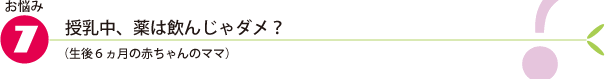


授乳中は、薬を飲むことに敏感になりやすい時期です。薬の副作用や赤ちゃんへの影響を心配して、具合が悪くても「薬は飲まない」とガマンするママも多いでしょう。
しかし現在では、さまざまな研究から授乳中でも安心して服用できる薬が増えています。そのため市販薬を購入するときは、必ず薬剤師に「母乳育児中です」ということを伝え、安全性の高い薬を選んでもらいましょう。
また病院に行くときも、医師に「母乳育児をしている」ことを伝え、母乳育児中でも服用できる薬を処方してもらいましょう。ときには「授乳は一時中断するように」と指示されることもありますが、そういうときは授乳をやめる前に、小児・内科など母乳育児に理解のある医師や助産師に相談してください。
薬を服用するタイミングは、授乳直後や赤ちゃんが長時間眠る前がベスト。また薬を飲んでいる間は、赤ちゃんの様子をよく観察し、(1)便がゆるい、(2)湿疹が出た、(3)吐く、(4)いつもよりよく眠るなど、異変に気づいたらすぐに小児科で相談しましょう。
万一、授乳を中止しないといけないときは、必ず搾乳して乳腺炎や母乳の出が悪くならないようにしてください。
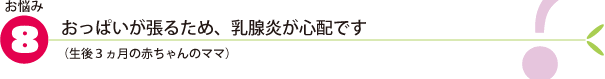
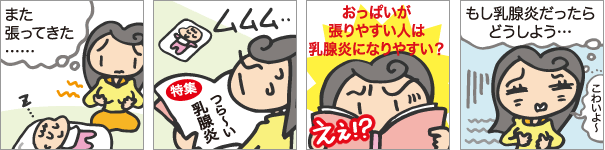
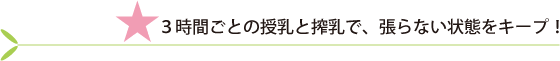
乳腺炎には、乳頭の傷などから細菌感染を起こす"細菌性乳腺炎"と、おっぱいに溜まった乳汁が腐敗して炎症を起こす"うっ滞性乳腺炎"がありますが、ほとんどの場合は後者の"うっ滞性乳腺炎"です。
おっぱいが張りやすいママは、乳汁が溜まったままにしておくと"うっ滞性乳腺炎"になりやすいので気をつけてください。
乳腺炎は急激に起きるのが特徴で、主な症状は片方の乳房の一部分が腫れて、熱を持ったり、ズキズキ痛み、1. 38℃以上の発熱、2. 悪寒、3. 関節痛などの全身症状を伴います。
予防策としては1. 昼も夜も3時間ごとの授乳間隔を守り、常におっぱいが溜まらないようにする、2. おっぱいが張ったり、飲み残しがあるときは搾乳しておく、3. 高カロリー、高脂肪の食事は食べ過ぎない、4. 疲れやストレスを溜めないことがキホンです。
もし乳腺炎になった場合は、とにかく赤ちゃんにしっかり・こまめ(3時間以内)に母乳を飲んでもらうことが大切です。痛いほうのおっぱいから先に授乳し、授乳後、黄色い(黄緑)ドロッとした乳汁が出てくる場合は、優しく搾り出してください。力を入れて搾ると、かえって悪化するので気をつけて!
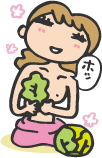
おっぱいが腫れて痛むときは、芯をとったキャベツを水で洗い、イラストのように腫れている部分に貼るとラクになりますよ。
また、保冷材をガーゼに包んであてたり、じゃがいも湿布もオススメです。
ただし、飲ませても良くならない時は、早めに助産師に相談しましょう。
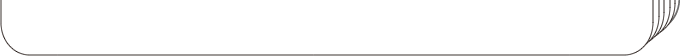




 左のバーコードを読み取りアクセス!
左のバーコードを読み取りアクセス!